

|
�@�����́A�ߑO���܂�A�ߌ�J�̗\��B �@���N��GW�́A�n����t�́A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p���A�����A���Ȃǂً͋}���Ԑ錾���A�ʼn߂������A�e���r��V���̕Ō������A�l�̓����ɂ���قnj����ȕω��������Ȃ��B������A�R���i�̊����҂͌���Ȃ��B
�@�����A�����͓s���őł����킹�̓������A�������U�����悤���A�ƍl���Ȃ���ʋo�b�O�̏���������B �@�s����͌��܂�Ȃ�����ǁA�Ƃ肠�����召2�̂��ɂ���������W�ʼn��߂āA�n���J�`�ɕ�݃o�b�O�ɕ��荞��ŏo������B �@10���߂��ɉƂ��o�āA�܂��̉��A���]�Ԃʼnw�O�i�Ƃ����Ă��A�w�܂�300���[�g�����炢�j�̎��]�Ԓu����ɋ}���B���̒��֏�͔N��4,500�~�B �@�V������œd�Ԃɏ��ƁA�����̂悤�ɂP�ԗ���10�l�قǂ̏�q�B
�i����ɂ��悤�I�j �@�����l���Ȃ��ŕ����A����̒��ɏ����ς�������̂�������U�����ǂ�����ǁA���͑ӂ����̂�����A�ړI�������Ɠr���Ŏ~�߂�\���������B �@ �@A1�Ԃ̏o������n��ɏo�����A�����A�ǂ���ɍs���Ηǂ��̂��H �@ �@�n�c�拳��ψ���ƁA���̊ێR���Ȃ����Ă����J�약�����~��(18���I����)�Ɠ����ɁA���R���l�Y���~��(19���I���Ή߂�)�̔肾�B�@ �@�X�e�����X�p�l���̕\�ʂ�����ɖ�����Ă���̂ŁA�ʍs���̎Ԃ�l�̎p���f���ĕ������ǂ݂ɂ������A��������Ƃ��Ă���ꂽ���j�������g���B
�@���J�약�������R���l�Y�����݂̐l���炵�����A��������͑n��ŁA�ǎ҂��y���܂��邽�߂̂��̂��B �@����̎U�������������ŁA�d�Ԃŏ�����ǂނ����m��Ȃ��B
�@���̂܂ܓ��ɕ����A�剡��ɓ�����Ɓu�e�싴�v������B���̍���O�ɂ͏����Ȉ�ׂ��K������A���̂܂��̍L�ꂪ�V���n�ɂȂ��Ă���B
�@�V���n�̒[����u�剡��e���X�v�Ɩ��t����ꂽ�V������쉈���ɖk�������B
�������̌����_�̕ӂ�Ɂu���J�약���̋��@�Ձv�i���J�약�����~�� �Ƃ͕ʁj������͂��Ȃ̂ŁA�����_���E�ɐ܂�ĒT����������Ȃ��B
�T�����ɍ���ƁA���͂����ɁA�����ɂ���l�ɐq�˂�B�X�Ŕ����������Ă��āA�ړI����������Ȃ��ƓX������Ɂu�Z�Z�͂ǂ̒I�̕ӂ�ɂ���܂����H�@�����Ƌ����Ă��炦�Ύ����ŒT���܂�����v�ƌ����āA���i�I�̗������āA���Ƃ͎����ł�������T���B
�@�����ł��X��̉Ԃɐ��������Ă��邨����Ɂu���̕ӂɒ��J�약���̋��@�Ղ�����炵����ł����A�����m�ł����H�v�ƕ����ƁA�u���A����Ȃ炻�̊p���Ȃ����Ă����̂Ƃ���̊v������ł���v�ƌ����B�Ԃ��ɗ����q�́A�m�荇���炵�������u����A�e��̉w�̂����c�v �u�����A�����B����͕ʂ̋����~�Ȃ́v�Ƃ��A�b���i�ނ̂ŁA���̃K�C�h�n�}�������āu�w�̋߂��̂����J�약�����~�Ձi���R���l�Y���~�Ձj�ŁA�ێR���Ȃ���̑O�ɂ���܂����B���̋߂��̂��ʂ́A���J�약���̋��@�Ղ炵���ł��ˁv �@�Ƃ����ƁA�u���������A����҂���̑O�ɂˁv�u�������̂͊v������̑O�v�Ƃ��A�Ȃ�Ƃ��b���Ȃ����āA����������āA��l���c���Ċp�����ɋȂ���B 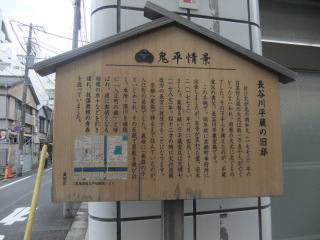
�p���琔���ڂ̊v���i�����E���́i���j�^�P�_�̓X��ɁA�]�ˎ���̍��D���H�ȕ��������Ă���B
�u�S����i�v�Ƃ��āA���J�약���̐��������⊈��������Ă���B
�e��w�O�̉��~�Ղ͎���҂���̃r�������A���]���̋��@�Ղ͊v������ɂȂ��Ă���B
�@�܂��e�Ɋp�A�u���]������i�Ăj�v�Ƃ��u�{���i�ق�j�̋S��i���ɂĂj�v�ƌĂꂽ�����̐t�̂���i�������A�r�g�����Y�̍�j�̓��]���A�܂荡�̖n�c��S���ڂɉ��Ƃ��H�蒅�����B �@�ʐ^�𐔖��B���āA���́u���̏��v�̐ՁB
�����A�i���͓c�ɂ���㋞�����u�悻�ҁv�Ȃ̂ŁA�Ԉ���Ă��邩���m��Ȃ����j���̕ӂ肩����c��̌������i�������j�͂ЂƐ̑O�́A�u�[�����[�g���n�сv�ƌĂ��Ⴂ�y�n���L����A�n�c�삪�×�����x�ɏ����E����Z���̔�Q�Ɍ�����ꂽ�n�悾�Ǝv���B
�剡��̎�O���獶�ɓ���ƁA���̑O�X�J�C�c���[����c�����̖T��������剡��e�������̎n�܂肾�B �O������̂́A���Ƃقړ��N��̒j���Ƃ��̑��炵���c���B
�@���͉͌��̌����ɍ~��āA
�@��̉E�݂�k���čs���ƁA�e�j�X�R�[�g�Ȃǂ�����A���̏��̍]�������z����ƒ����`�̎Ő��≓�i�ɃX�J�C�c���[��������B
�@�͌��ɂ���������ɍ~���ƁA�Ő��ł͂܂����^�����^���P�����Ă��邩�Ǝv���ƁA���҂͑ւ���āA1�ˉ߂����炢�̗c���̕��s�P���H������Ⴂ�v�w�ɂȂ��Ă���B
�@���x�x���`��3�r���Ă���̂ŁA���̒��̂ЂƂŋx�e�ƃ����`�^�C���ɂ���B
�@�Ƃ��o�Ă���6000���Ȃ̂ŁA�e��w����1���ԁA60�p��6000����3.6�q�قǕ��������ƂɂȂ�B
�@���������x�A�����̒��H���Ԃ�12�����B
�@��͉_�ɕ����Ă��邪�A���͑u�₩�ŁA�H���̌O���Ƃ����Ƃ��납�B
�@�{���Ȃ�A�O�ɒu�����y��P�[�X�Ƀ`�b�v������Ƃ��낾���ǁA�Ȃ�ƂȂ����������āA��������ʐ^�����B���Ă������B�@ �@�i��ăt�H�[�N�œ��{�݂̂�Ȃ��y���܂��A���{�ł̑؍݂��y����ŋA���Ă��������j�Ǝv���Ȃ���AJR�ɘ������B
�{���̕����@12,700�� �@�������́i�`�F�b�N�|�C���g�j�����Ȃ����ɂ́A���������ɕ����Ă����B
|
| �@ |
| �@ |